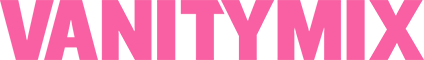People In The Box 10th Anniversary『The Final』ライブレポート@EX THEATER ROPPONGI 1月21日(日)
自身の音楽性の姿勢や真摯さを立証した
People In The Boxの10周年記念イヤー締めくくりライブ

ステージ上から放たれた音楽を、ただ全身で享受する観衆。そして、その独自の音楽性が描く世界に、集まった各人が思い思いに、ここではない何処かへ誘われ、そこに居る自分を顧みている……。それはここ10年間、ほぼ変わっていない光景でもあった。
2017年にデビュー10周年を迎えたPeople In The Boxが、六本木のEXTHEATERにてライブを行った。昨年1年をかけて行ってきた様々なアニバーサリー企画/ライブ/ツアーを締めくくるべく臨んだ、この日。数曲ではあったが、1月24日発売の3年半ぶりのニューアルバム『Kodomo Rengou』からの楽曲の一足早い披露を含め、過去からの曲もふんだんに織り交ぜた、彼らの来し方行く先が伺える内容であった。
例え広いステージだろうが、ライブハウスだろうが、会場の大きさやステージの広さに関係なく、基本、彼らのセッティング位置は変わらない。この日も、お互いがアイコンタクトを取れる距離で、広いステージの中心に半弧を描くように機材類が並ぶ。


 3人が登場。スタンバイするも1曲目を始めるまでに、ちょっとしたインターバルが置かれる。つま先立ちしているかのような緊張感。それを煽るように奏でられるデモンストレーション音。その中からボーカル&ギターの波多野裕文が「People In The Boxです。よろしくお願いします」とライブの開始を告げる。オープニング曲は“汽笛”。厳かな空気をパーっと切り裂くように、生命力と解放感が場内に広がっていく。まるで気持ちの良い朝を迎えたような清々しい気持ちだ。続いては、“火曜日 / 空室”。ここでは静と動の共存が楽しめた。ベースの福井健太の運指(うんし)がグリグリとライブを進めゆく。次の“聖者たち”ではスリリングさが会場を支配した。波多野もトリッキーな譜割りで歌い、場内を聖者たちの行進へと誘う。
3人が登場。スタンバイするも1曲目を始めるまでに、ちょっとしたインターバルが置かれる。つま先立ちしているかのような緊張感。それを煽るように奏でられるデモンストレーション音。その中からボーカル&ギターの波多野裕文が「People In The Boxです。よろしくお願いします」とライブの開始を告げる。オープニング曲は“汽笛”。厳かな空気をパーっと切り裂くように、生命力と解放感が場内に広がっていく。まるで気持ちの良い朝を迎えたような清々しい気持ちだ。続いては、“火曜日 / 空室”。ここでは静と動の共存が楽しめた。ベースの福井健太の運指(うんし)がグリグリとライブを進めゆく。次の“聖者たち”ではスリリングさが会場を支配した。波多野もトリッキーな譜割りで歌い、場内を聖者たちの行進へと誘う。
この日は、10年前の楽曲たちも披露された。「この10年間の幕開けの曲」(波多野)の言葉と共に、“She Hates December”が、当時よりもダイナミズムを帯びた演奏で贈られる。また、続く“犬猫芝居”では、変拍子を交えた幾何学な音楽ながら、ことさらスムーズなプレイが堪能できた。
序盤後半のブロックでは、二ューアルバム『Kodomo Rengou』からも数曲披露された。“無限会社”はグイグイと切迫感のある曲。3人一丸のハーモニーも印象深かった。また、“デヴィルズ&モンキーズ”では、ラストに向け、この上ない高みへと引き上げてくれた。しかし、お客さんも良い意味で、この10年間、リアクションが変わっていない。これだけ躍動的でめまぐるしい曲ながら会場が微動だにしないで魅入っている光景も、変わらず。そう、今も昔も、各曲毎に観衆が、ここではない何処かへと誘われている証拠だ。と同時に、その光景は、ずっと彼らを見続けている者と近年ファンになった者たち同士の信頼感のようにも映った。



 中盤では、波多野もギターから鍵盤へとパートを変え、より美しさが交えられた数曲が披露された。フロア頭上の巨大なミラーボールが回る至福と刹那のなか歌われた“月”、フリースタイルのハミングも特徴的だった“技法”、また、久々に聴けた“レテビーチ”では、より抜き差しによるドラマティックさも堪能出来、“大砂漠”では、3人揃って一丸となって攻めてくるよう感覚をおぼえた。
中盤では、波多野もギターから鍵盤へとパートを変え、より美しさが交えられた数曲が披露された。フロア頭上の巨大なミラーボールが回る至福と刹那のなか歌われた“月”、フリースタイルのハミングも特徴的だった“技法”、また、久々に聴けた“レテビーチ”では、より抜き差しによるドラマティックさも堪能出来、“大砂漠”では、3人揃って一丸となって攻めてくるよう感覚をおぼえた。
ドラムの山口大吾による恒例の愛着のあるディスりも交えた物販紹介のあと、6月からは全国ツアーを行うことを報告。会場を湧かせた。そして、「11年以降もぶっ放していくのでよろしく!!」(山口)と、MCを締め、そのままラストスパートへ。
中期の頃、ライブで頻繁にプレイされた“ニムロッド”、更にスリリングさが増し、波多野のポエトリーリーディングも記憶に深い“旧市街”、一緒に行こうぜと誘うかのような“木洩れ陽、果物、機関車”では、眩しく神々しく、光に包まれるように希望の約束の地に連れ出してくれた。本編ラストは「10周年の最後は一番新しい曲」(波多野)と“かみさま”。神々しく、何かに感謝したくなり、まるで朝日を浴びているような活力溢れる楽曲が慈しみを込めて会場中に放たれた。
アンコールでは、山口による淡々とした長いリズムキープの中、“ヨーロッパ”が現れた。最後も突き進むかのような歌だ。エモーショナルに広がっていく同曲。波多野によるポエトリーリーディングも合わせて広がっていく。「君の胸騒ぎが本当になるといいな」は、相変わらず印象的なフレーズだ。神々しい光に包まれるかのような浄化された気持ちを残して、彼らはステージを去り、10周年記念イヤーは幕を閉じた。
一体感や共有感に頼らない、自分たちだけの音楽性だけでの勝負の仕方…。音響、ポストロック的な立ち位置の出自から、その変わることのない姿勢と、ブレのない音楽性。そこに常に帯同させてきたポピュラリティ。「ダンスロックだ!」「シティポップだ!」「EDMだ!」とトレンドが変わり、それらを自己に取り入れて進化したり、変化しているバンドも多い。しかし、振り返ると彼らは違う。その3ピースという最小限のロックバンドフォームで、技巧を最大限に駆使しながらも、それを感じさせないほど、<普通に聴けるが独創性溢れるポップス>として昇華させてきた。楽曲の成長や進化、今ならではのアレンジ等を織り交えながらも、この日、彼らが魅せてくれたのは、そんな変わらない<自身の音楽性の姿勢や真摯さ>のようにも映った。
11周年以降のPeople In The Boxもきっと、いや、絶対に逞しい。まさに、それを強く確信させてもらった一夜でもあった。
Text:池田スカオ和宏(LUCK’A Inc)
Photo: takeshi yao