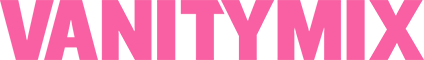自分に制限をかけず、ギャップを出せるような女優になりたい

2008年、日本の新国立劇場と韓国の芸術の殿堂(ソウル・アート・センター)のコラボレーションで製作され、演劇賞を総なめにした舞台『焼肉ドラゴン』が映画化。万国博覧会が催された1970年、関西の地方都市の一角で焼肉店「焼肉ドラゴン」を営む家族を描いた今作で、一家の三女・美花を生き生きと演じた桜庭ななみ。個性豊かな登場人物の中でもきらりと光る存在感を見せた彼女に、製作現場について、そして美花について話を訊いた。
■美花役を演じられていかがでした?
桜庭 すごく活発な女の子で、その中でもいままでとは違った役どころだったので、撮影中は闘いというか、新しくチャレンジしていく部分が多く完成がどうなるかドキドキしてたんですけど、この家族の一員としてやりきれたかなと思っています。
■闘いというのは具体的に言うとどんなところです?
桜庭 話し方とかですね。自分がイメージしてたものを現場に持って行ったんですけど、監督がイメージしてるものがあったので、それを自分の中に入れるまでにちょっと時間がかかってしまって。でもひとつひとつ丁寧に監督が指導してくださったので、最後まで演じることできました。
■監督のイメージと違ったところというのは?
桜庭 細かく言うと声の出し方とかガサツさみたいなものを少し足すとか、そういうところですね。そういう細かいところが撮影をしていく中でどんどん入ってきて、それによって美花ができていったんですけど、最初はちょっと探り探りという感じでした。
■撮影しながらつかんでいった感じですか。
桜庭 家族の雰囲気や現場の雰囲気も全部そうなんですけど、撮影しながら作っていった感じです。
■もととなった舞台はご覧になってました?
桜庭 観ました。それぞれのキャラクターにそれぞれ届けるメッセージがあって、わたしもこういうふうに演じられたらいいなと思ってましたけど、みなさん素晴らしいお芝居をされていたのでプレッシャーもありました。監督もみなさんもすごくいい作品になるっていう自信を持っていたので、それをわたしが邪魔をしてはいけないというか。
■なるほど。
桜庭 あとは、美花という役は韓国語も日本語もどちらも話して、しかもどちらもすごく上手なんですよ。そこも上手くできるか不安だったんですけど、今回韓国の俳優さんたちが親身になってくださって、セリフ一言一言の発音をとても丁寧に教えてくださって、すごく助かりました。
■それは心強いですね。
桜庭 はい。現場がすごく熱かったんです。自分はこういうふうにお芝居をしたい、こういうふうに届けたいって、監督もそうですけどキャストのひとりひとりがみんなそういう熱い想いを持っていて。ほんとにみなさん熱くて素敵な方たちでした。
■美花は自由奔放な女の子で、奥さんのいる方とおつきあいをしていますが、奥さんとのやりとりもおもしろかったですね。
桜庭 あのパワフルな奥さんに立ち向かう美花ってすごいなって思いました。(笑)自分が演じてるからヒイキしてるのかもしれないですけど、応援したくなるようなカップルというか。
■ピュアですよね。お母さんには反対されてましたけど。
桜庭 最初は反対するんですけど、それでも自分の子どもだからって最終的には許してくれる、そのつながりも素敵だなって。やっぱり家族だからどんなことがあっても自分のいちばんの味方であってくれるし、お母さんと美花は実際に血がつながってる親子なので、そのやさしさがすごく伝わるシーンなんじゃないかと思います。
■みんな明るいんだけどそれぞれ胸に秘めた想いがあって、でもぶつかるときは本音でとことんぶつかるっていうその関係がすごく素敵だと思いました。
桜庭 なんでも本音をぶつける家族だからこそいろんな事件が起きてくると思うんですけど、家庭の色というか、家族の色みたいなものがしっかり出てますよね。撮影中も熱がありすぎてセットが揺れてましたから。(笑)
■すごいパワーですね。
桜庭 もうみんなのパワーがすごくて、わたしもとにかく暴れるというか、自分の気持ちも伝えたいと負けられない!と思って演じていました。
■こういう役をやられて、演技に対する考え方などで変わった点はあります?
桜庭 いままでは自分が納得するお芝居というか、自分がこうだと思ったらこうっていうお芝居をやってきたんですけど、今回は監督がいろいろ指導してくださって、自分にないお芝居を引き出して頂いたと思うし、自分では見えなかったことが見えてきたので、すごくいい経験をさせてもらったと思います。
■ここまで振り切った役をやられたら、また今後チャレンジしたい役もいろいろ出てきたんじゃないでしょうか。
桜庭 今回は自分で想像したこともないような役だったんですよね。同じ明るいにしても、一生懸命でまじめな役はあったんですけど、今回はまた違った明るさの役で。でも今回やらせていただいて、また自分になかった部分を出せるような役もやりたいと思いましたし、自分に制限をかけず、こういう役もやるんだ、みたいなギャップを出せるような女優になりたいです。
Interview & Text:藤坂綾